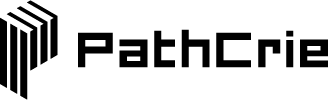「2024年問題で物流が止まる」
──2024年4月、法改正によってドライバーの労働時間が制限され、輸送力の低下やコスト上昇が懸念されていました。2025年を迎えた今、物流の現場では何が起き、EC事業者にはどのような影響が出ているのでしょうか。
本記事では、2024年問題の“その後”を振り返りつつ、現場で起きた実際の変化と、次に懸念される「2030年問題」についても解説します。
2024年問題とは何だったのか
働き方改革関連法による「時間の壁」
2024年問題の根幹にあるのは、2019年に施行された「働き方改革関連法」です。この法律は、多様な働き方に対応し、労働環境を改善することを目的にしています。多くの企業では上限規制がすでに適用されていましたが、建設業、運送業、医師など一部の業種には適用が猶予されていました。この一部の業種でも2024年4月1日から残業時間の上限規制が本格的に適用されることになりました。これが「2024年問題」と呼ばれる所以です。
特に物流業界に関わる大きな変更点が、自動車運転業務における時間外労働の上限規制です。具体的には、年間960時間という上限が設けられました。これは月平均にすると80時間、いわゆる「過労死ライン」と言われる時間であり、ドライバーの長時間労働を是正し、健康を守るために必要不可欠なものとして導入されました。
なぜ物流業界が影響を受けたのか
なぜ、数ある業界の中でも物流業界が2024年問題の影響を受けると言われたのでしょうか。
まず、物流業界は慢性的な人手不足に陥っています。全日本トラック協会の資料によると、有効求人倍率は常に高い水準にあり、特に長距離ドライバーは高齢化が進み、若い担い手が増えていないのが現状です。
こうした背景の中、これまでドライバーは長時間労働によって、なんとか需要をまかなってきました。しかし、2024年4月から労働時間の上限が法律で定められたことで、これまでと同じ働き方ができなくなりました。
物流の現場は、まるで大きな水の流れをせき止めるダムに、突如として壁ができたようなものです。ドライバーの労働時間が物理的に制限されるため、同じ物量を運ぶためには、より多くのドライバーが必要になります。しかし、人手不足の現状ではそれが難しく、結果として輸送能力の低下やコスト上昇につながると懸念されていました。
制度施行から1年、今振り返る“当初の懸念”
2024年問題は「物流の危機」とまで言われ、さまざまなメディアで取り上げられました。特にEC事業者にとっては、「明日から荷物が届かなくなるのでは?」「配送料が急激に上がるのでは?」といった不安がつきまとっていた方も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、2024年問題による社会的な大混乱は、今のところ起きていません。
しかし、これは「何も問題が起きなかった」ということではありません。現場レベルではさまざまな変化が起きていて、水面下で静かに、しかし確実に変化が進んでいます。
特にEC事業者の多くが直面している課題として、以下のようなものがあります。
・想定より配送料が上がってしまい、利益が圧迫されている
・特定エリアへの配送が難しくなったと言われた
・自社だけでは解決できない配送トラブルが増えた
こうした問題は、2024年問題が引き金となり、物流業界全体に少しずつ波紋を広げているのです。
2024年問題はどうなった?物流現場の今

ドライバー不足は解消されたのか?
残念ながら、ドライバー不足は解消されていません。むしろ、労働時間の制限によって、より深刻な問題になりつつあります。
これまでは、経験豊富なベテランドライバーが、長距離・長時間運行をこなすことで、全体の輸送量を維持していました。しかし、労働時間が制限されたことで、ベテランの力が十分に発揮できなくなり、一人ひとりの輸送力が低下しています。
この穴を埋めるためには、新たなドライバーを雇う必要がありますが、現実は簡単ではありません。賃金水準や労働環境の課題から、依然としてドライバー志望者は少ないままです。この状況は、EC事業者の「即日配送」や「時間指定配送」といったサービスにも直接的な影響を与え始めています。
輸送力の減少は本当に起きたのか?
輸送力の減少は、全国的に見ればまだ「劇的に起きた」とは言えないかもしれません。しかし、現場ではすでに輸送力のひずみが生まれています。
特に、地方の配送は影響を受けやすい傾向があります。長距離の運送ができなくなったことで、荷主や物流会社は、中継地点を設ける「中継輸送」や、複数の事業者が協力して荷物を運ぶ「共同輸送」といった方法を取り入れています。これにより、荷物の到着が遅れたり、場合によっては追加費用が発生したりするケースが出てきました。
また、繁忙期には、これまで当たり前だった配送キャパシティが確保できなくなり、予定していた出荷が遅延するといったトラブルも起き始めています。
運賃や物流コストに生じた“静かなインフレ”
物流コストは確実に上昇しています。これは、ドライバーの労働時間制限によって、これまでのような「安く・早く」運ぶことが難しくなったためです。
物流会社は、ドライバーの給与水準を維持し、新たな人材を確保するために運賃を上げざるを得ません。多くの企業が、燃料費や人件費の高騰分を運賃に転嫁する動きを始めており、この「静かなインフレ」は今後も続くでしょう。
EC事業者の中には、配送料の値上げを余儀なくされた方もいるかもしれません。しかし、送料を上げることは顧客離れにつながる可能性もあり、非常に難しい経営判断を迫られています。
EC物流に起きた変化と、新たな課題
即日配送や送料無料モデルの限界
2024年問題は、EC業界に深く根付いていた「即日配送」や「送料無料」というビジネスモデルの限界を浮き彫りにしました。
これまで消費者は、ECサイトで注文すれば翌日には商品が届くことを当たり前のように期待してきました。しかし、この期待に応えるためには、配送業者に大きな負担がかかります。また、送料無料モデルも、実際には配送料が商品価格に上乗せされているだけで、そのコストはEC事業者が吸収していました。
物流コストが上昇する中で、これらのモデルを維持することは困難になりつつあります。消費者の利便性と持続可能な物流体制を両立させるために、EC事業者は、これまで当たり前だったサービスを見直すタイミングを迎えています。最近では、「置き配」や「コンビニ受け取り」など、ドライバーの再配達負担を減らす配達手段が少しずつ浸透しています。
中小ECの“配送品質格差”が広がる背景
大手のECモールなどは、強大な交渉力と物量を背景に、比較的安定した配送網を維持しています。しかし、中小規模のEC事業者はそうはいきません。
契約している配送会社の運賃改定やサービス内容の変更に、個別に対応するのは非常に難しいのが現実です。また、配送業者が契約を見直す際、物量の少ない中小企業は、優先順位が低くなってしまうこともあります。
結果として、大手と中小ECの間で配送品質に格差が生まれる可能性が出てきました。消費者は、同じ商品を注文しても「届くまでの時間」や「送料」が違うことに気づき始めており、これが顧客満足度にも影響を与えかねません。
返品・再配達をめぐる構造的課題が顕在化
再配達問題は、以前から物流業界の大きな課題でした。そして2024年問題によって、その深刻さが改めて浮き彫りになっています。
ドライバーの労働時間が制限されたことで、再配達にかかる時間や労力は、これまで以上に大きな負担となります。これは、ドライバーの負担を増やすだけでなく、再配達の手間によって、本来運ぶべき荷物が滞る原因にもなりかねません。
また、ECサイトでは「返品無料」を謳うサービスも多いですが、この返品物流にもコストがかかります。返品された商品を検品し、倉庫に戻す作業には人手が必要ですし、輸送にもコストがかかります。このようなコストは、最終的にEC事業者の利益を圧迫します。
EC物流の“いま”
事業者ごとに分かれた対応力の差
EC事業者の間では、2024年問題への対応に大きな差が生じていると考えられます。
●対応が遅れている事業者
・配送料の値上げは、まだ様子見している
・配送会社との契約を見直せていない
・在庫管理や返品対応の仕組みが不十分
このような事業者は、利益率の悪化や配送トラブルに直面しやすい傾向があります。
●すでに対応を進めている事業者
・配送会社を複数利用して、リスクを分散した
・一部の配送エリアを見直し、効率的な運用を始めた
・返品・交換ルールを明確にし、顧客にも協力を求めた
こうした事業者は、コスト増を抑えつつ、安定した配送品質を維持できているケースが多いとされています。
3PLを取り入れた企業が得た安定供給と柔軟性
2024年問題の対応策として、サードパーティ・ロジスティクス(3PL)を導入するEC事業者が増えています。3PLとは、企業の物流業務全体を専門の事業者にアウトソーシングするサービスです。
3PLを導入した企業は、自社だけでは解決できない課題を乗り越えやすいということです。複数のお客様の物流をまとめて請け負うことで、スケールメリットを活かし、運賃交渉や配送網の最適化を進めることが可能です。
また、突発的な物量変動にも柔軟に対応できます。繁忙期に急に荷物が増えても、専門の倉庫や人員を確保できるため、出荷の遅延を防ぐことが可能です。これは、自社で物流を完結させている企業では難しい対応です。
配送トラブルを防ぐ“仕組みの設計”が重要に
2024年問題は、物流の現場が単なる「モノを運ぶ場所」ではなく、「ビジネスの信頼性を支える重要なインフラ」であることを改めて示しました。
これからは、単に安く運ぶことよりも、「いかにトラブルなく、安定して運べるか」が重要になります。そのために必要なのが、物流の仕組みを設計することです。
例えば、
・注文から出荷までの時間を短縮するための倉庫内作業の最適化
・配送状況を顧客がリアルタイムで確認できるシステムの導入
・返品理由を分析し、返品を減らすための施策
といった取り組みは、すべて配送トラブルを防ぎ、顧客満足度を向上させるための仕組みです。これらの仕組みを自社で構築することが難しい場合、物流の専門事業者による支援によって、現場の実態を踏まえた最適な仕組みづくりが可能となります。
次に待ち受ける2030年問題とは
2024年問題は、業界全体の努力で大きな混乱を回避しましたが、課題が解決したわけではありません。次に控えているのは、さらに深刻な「2030年問題」です。
人口減少と高齢化が及ぼす影響
2030年問題の核心は、人口減少と高齢化です。
国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によると、2030年には生産年齢人口(15〜64歳)が現在の6割程度まで減少すると言われています。これは、ドライバーを含む労働力人口がさらに減ることを意味します。
また、高齢化が進むことで、物流サービスを必要とする高齢者が増える一方で、そのサービスを担う働き手が減っていくという構造的なひずみが、より顕著になるでしょう。
都市部と地方で異なる課題
2030年問題は、全国一律に影響を及ぼすわけではありません。
・都市部:物量が増え続ける一方で、人件費や地価の高騰により、物流コストがさらに上昇する可能性があります。また、交通渋滞による配送遅延も課題となるでしょう。
・地方:人口減少により、採算が取れないエリアが増え、配送サービスから撤退する事業者が増える可能性があります。物流の空白地帯が生まれるリスクが高まります。
企業が今から準備すべきこと
2030年問題に備えるために、企業が今から準備すべきことは明確です。
●テクノロジーの活用
・ロボットや自動化技術を導入し、倉庫作業の省人化を図る
・AIを活用した配送ルートの最適化で、効率を上げる
●物流体制の再構築
・3PLなどの専門パートナーと連携し、自社の物流をスリム化する
・複数の配送会社と契約し、リスクを分散する
・共同配送や中継輸送など、新しい輸送方法を検討する
●顧客とのコミュニケーション
・送料無料モデルを見直し、適正な配送料を顧客に理解してもらう
・即日配送が難しい場合は、事前にリードタイムを伝えることでトラブルを防ぐ
・置き配やロッカー受け取りなど、再配達を減らす選択肢を増やす
まとめ
2024年問題は、物流業界が抱える課題を社会全体に知らしめるきっかけとなりました。大きな混乱は回避されたものの、その影響は水面下でEC事業者様に確実に及んでいます。
ここ1年の動向から、EC物流では「安さ」や「早さ」だけでは持続的な運営が難しいことが明らかになっています。次に控える2030年問題にどう備えるかが、今後の焦点です。
今後、EC事業を成功させるためには、物流を単なる「コスト」としてではなく、「競争力」の源泉として捉え、持続可能な体制を築くことが急がれます。
もし、貴社の物流体制に不安があるようでしたら、ぜひご相談ください。私たちパスクリエが提供するEC特化の物流サービス『LogiPath』は、中小規模のEC事業者様でも大手並みの物流体制を構築できるよう、現場の知見と技術を組み合わせたご提案をしています。EC物流のプロフェッショナルである私たちも、現場で培った知見を活かし、皆様のビジネス成長に貢献したいと考えています。

▼60サイズ580円で始められる、従量課金制のEC物流サービス「LogiPath」
https://pathcrie.co.jp/logipath/