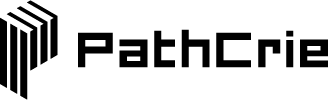- 2025/09/22
- EC販売戦略

目次
SNSやECの進化とともに広がった「D2Cブランド」は、いまや新しいトレンドというより、多くの企業が取り組む一般的なビジネスモデルとなりました。競合が増えたことで、単に商品を販売するだけではなく、ブランドとしてどのように顧客と関係を築くかが問われています。本記事では、定番化したD2Cブランドが直面する課題と、その成長を支える物流戦略について解説します。
D2Cブランドとは何か?
D2C(Direct to Consumer)ブランドとは、メーカーが中間業者を介さずに消費者へ直接商品を販売するビジネスモデルを指します。ECサイトやSNSを活用し、マーケティングから販売、アフターサービスまでを一貫して自社で管理する点が特徴です。
このモデルは、単なる直販ではありません。ブランドの世界観や価値観を明確に発信し、ユーザーとの関係構築を重視することで、ファンの共感と支持を得ながら成長していくのがD2Cブランドの本質です。
小売モデルとの違い
従来の小売では、メーカーから卸業者や小売店を経由して商品が消費者に届きます。一方、D2Cブランドは製造から販売までのバリューチェーンを自社でコントロールするため、ブランド戦略を直接反映した商品・体験設計が可能です。価格設定や顧客との接点も自社で最適化できることから、高いブランドロイヤリティを構築しやすいのが強みです。
なぜD2Cブランドが注目されるのか
SNSとネットショップの普及によって、社員が数名しかいない会社でもD2Cブランドを立ち上げやすくなりました。たとえばInstagramで商品を紹介し、BASEやShopifyで販売を始めるといった流れで、広告費を大きくかけずにスタートできるケースが増えています。さらに、消費者の関心が「安さや便利さ」だけでなく「ブランドの考え方やストーリー」へと移りつつあり、共感を大切にした購買体験を提供できるブランドが支持されやすくなっています。
D2Cブランドが直面する3つの課題
D2Cブランドは柔軟かつスピーディに立ち上げが可能である一方で、成長と持続に向けた課題も多く存在します。特に、ブランド構築・在庫運用・物流体制の3点は事業継続の成否を分ける重要なポイントです。
顧客体験とブランドストーリーの設計
D2Cブランドの強みは、単に商品を販売することではなく、ブランドのストーリーを通じてファンとつながることができる点にあります。ただし、その世界観を商品ページや配送体験まで一貫して表現するのは簡単ではありません。たとえばアパレルであれば、撮影写真のトーンとパッケージの色味をそろえる必要があります。食品であれば、同梱するリーフレットやレシピカードを通じて「食卓をどう楽しんでほしいか」を伝えることが大切です。ページのデザイン、梱包材、同梱物まで細部に一貫性を持たせてこそ、ブランド全体の一体感が顧客に伝わります。
在庫リスクと商品の回転率
D2Cブランドは流通在庫を持つ以上、在庫リスクの見極めと商品回転率の管理を避けて通ることはできません。たとえば需要予測を誤れば、人気商品が欠品して販売機会を逃す一方で、売れ残りの商品が倉庫に滞留し、キャッシュフローを圧迫します。特に小規模なD2Cでは、余剰在庫が資金繰りに直結するため、リアルタイムで販売データを把握し、状況に応じて柔軟に発注を調整できる体制が求められます。
ロジスティクスの最適化
商品が消費者の手元に届く瞬間は、D2Cブランドにとってブランド体験の仕上げともいえる重要な場面です。もし配送が遅れたり、注文と違う商品が届いてしまうと、それまでのストーリーや商品の魅力が一瞬で損なわれてしまいます。たとえばSNSで「届くのが遅い」「梱包が雑だった」といった声が広がれば、顧客満足度の低下だけでなくブランドの信頼性そのものが揺らぎます。立ち上げ当初は代表者や少人数で発送対応できても、注文数が増えると限界が訪れます。だからこそ、成長に合わせてプロの物流体制へ移行する判断が必要になります。

EC物流の視点から見るD2Cブランドの強化策
EC物流は単なる「配送手段」ではなく、顧客体験を完成させる最終工程です。D2Cブランドが成長するためには、物流を単なるコストではなく、マーケティングと同様に戦略的に捉える視点が求められます。
初動の在庫管理がブランド成長を左右する
ブランドを立ち上げたばかりの段階では、需要の予測が難しく、さらに資金面でも余裕がないため、過剰在庫・欠品リスクの両面に備えた在庫設計が求められます。SKU数が少なくても、カラーバリエーションやサイズ展開があれば、棚管理は複雑化します。適切なロケーション設計やWMS(在庫管理システム)の導入も、早期に検討すべき項目です。
リードタイムと配送体験の最適化
配送スピードは顧客満足度に直結します。商品が注文されてから手元に届くまでの時間=リードタイムが長いと、期待値が下がり、結果的にレビューやリピート率にまで影響します。出荷処理のタイミング、倉庫の立地、配送業者の選定など、全体を見据えたリードタイム設計が欠かせません。また、梱包資材や同梱物にブランドの世界観を反映することも、配送体験の価値を引き上げる重要な要素です。
返品・交換対応でファン化を促進
D2Cブランドにおいて、返品対応は“コスト”ではなく“信頼構築の機会”と捉えるべきです。問い合わせ対応から返品受領、在庫戻しまでの流れをスムーズにし、ユーザーの不安や不満を最小化することが、ブランドへの信頼やリピート購入につながります。
成功するD2Cブランドに共通する3つの視点
D2Cブランドで継続的に成果を上げている企業には、いくつかの共通点があります。とくに、「ユーザー理解」「運用体制」「物流戦略」など物流の仕組みを部分ごとではなく一体で捉え、調整しながら運営している企業が多いです。
ユーザー理解とデータ活用
SNS上の反応やカート離脱データなど、ユーザーの“行動”からインサイトを得る力がブランド設計に直結します。D2Cではリアルタイムな改善が可能ではありますが、分析・改善の速度が求められます。商品開発やCX改善への活用がブランド価値を高めます。
内製と外注のバランス
全工程を内製化しようとすると、初期投資や人的負荷が大きくなります。商品づくりやブランドの発信は内製化し、物流やカスタマーサポートは外部の専門会社に委ねるなど、役割分担を明確にすることが、組織の中長期的な成長の鍵となります。
物流パートナーとの連携
とくに物流においては、単なる委託先ではなく、共にブランドを育てるパートナーとしての関係性が重要です。波動対応、複数販路への出荷、SKU管理など、細かなニーズに柔軟に対応できる物流体制こそが、顧客満足を支える土台となります。
まとめ:D2Cブランドに必要なのは共感と徹底した体験設計
D2Cブランドが成功するかどうかは、「どれだけ共感されるストーリーを描けるか」だけでなく、そのストーリーを最後まで一貫して届けられるかにかかっています。製品設計・サイト体験・梱包・配送・アフターサポートまでがひとつの“ブランド体験”であると考え、物流品質にも妥協しないことが、中長期的な成長につながります。
EC物流の支援に強いパートナーを選ぶなら「LogiPath(ロジパス)」

D2Cブランドの成長には、単なる配送業務ではなく、ブランドの世界観を壊さないよう物流設計に踏み込んで提案できる会社を選ぶことが大切です。たとえば、株式会社パスクリエが提供するEC物流代行サービス「LogiPath(ロジパス)」では、在庫の初期設計から受注波動への対応、返品処理までを一気通貫で支援しています。
・ブランドに合わせた梱包や同梱物の演出まで手が回らない
・複数の販売チャネルを運営しており、在庫管理が煩雑になっている
・返品処理や交換対応に時間を取られ、本来のマーケティングに集中できない
といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
▼60サイズ580円で始められる、従量課金制のEC物流サービス「LogiPath」
https://pathcrie.co.jp/logipath/