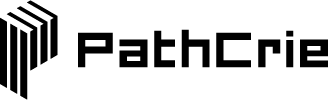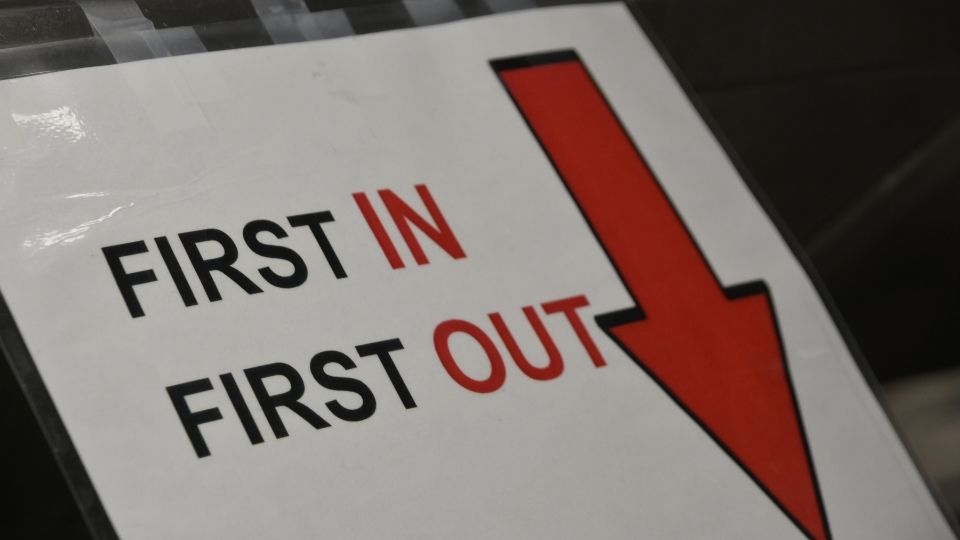
目次
在庫管理の基本である「先入れ先出し」。名前は聞いたことがあっても、実務でどのように活用するのかを正しく理解している方は、意外と少ないかもしれません。本記事では、EC物流の現場目線から、先入れ先出しの意味や効果、現場での運用上のポイントまでを具体的に解説します。
そもそも「先入れ先出し」とは何か?
「先に入れたものを先に出す」というルールの意味と背景
「先入れ先出し」とは、倉庫に先に入庫された商品を、先に出庫するという在庫管理の基本ルールを指します。英語では「FIFO(First In, First Out)」と表現されることもあります。
この運用は一見単純に思えますが、「実際の出荷順」と「入庫日・ロット管理」が正確にリンクしているかが重要になります。入庫順が把握できていなければ、見た目は先入れでも、実際は後から入った在庫を先に出してしまうケースも少なくありません。
「在庫回転率」「品質管理」との関係性
先入れ先出しは在庫の鮮度を保つうえで必要な管理方法です。とくに、食品や化粧品など賞味期限・使用期限のある商品を扱うEC事業者にとっては、このルールの徹底が品質管理に直結します。
なぜ「先入れ先出し」が物流現場で重要なのか
現場で「先入れ先出し」を守るべき理由は、主に3つの観点から説明できます。
消費期限・賞味期限がある商品では必須ルール
まず1つめは、品質の維持です。特に消費期限やロットごとの使用期限が存在する商材では、在庫が古くなることでクレームや返品につながるリスクが高まります。倉庫での作業が煩雑になる繁忙期ほど、このルールを守ることが事故防止につながります。
在庫評価や棚卸精度の向上にも直結する
2つめは、在庫評価・棚卸精度の観点です。古い在庫が長く滞留していると、帳簿上は在庫として残っていても、実質的には販売不可能な“死に筋在庫”となります。
出荷ミス・返品削減に繋がる作業の仕組みづくり
3つめは、業務の標準化という意味での重要性です。先入れ先出しを基本方針として定めておくことで、アルバイトや派遣スタッフを含む全体の作業精度を均一化しやすくなります。結果として、出荷ミスや返品の削減にもつながります。
現場での運用方法とよくあるトラブル
実際の現場では、「先入れ先出し」をただマニュアルに記載しただけでは機能しません。物流現場での実行力は、仕組みと導線の設計にかかっています。
ロケーション管理と組み合わせた運用のコツ
たとえば、ロケーション管理(在庫の保管場所管理)で、1つの商品を決まったひとつの棚や場所にだけ保管し、、古い順から取り出せるような物理設計があるだけで、現場での取り違えが激減します。
「見た目は先入れなのに実際は後入れ」になりやすいケース
また、棚に並べたときの“見た目”に頼ってしまうのも、よくある落とし穴です。パレット上の在庫が積み直されていたり、作業者によって配置が変わっていたりすると、実際の入庫順とは異なる在庫を先に出荷してしまうことがあります。これは、「なんとなく取ったら、実は後入れ先出しになっていた」というパターンで、結果として不良在庫やロスを招きます。
現場ではこうしたトラブルを防ぐため、WMS(倉庫管理システム)で入庫日やロットを紐付けた管理を行い、システム上でピッキング順を制御するケースも増えています。それでも最後は作業者の判断に委ねられる場面もあるため、現場への教育もあわせて行うことが、運用を定着させるポイントです。
自社で導入する際の注意点と成功のポイント

「うちも先入れ先出しにしよう」と思っても、単純に倉庫作業の手順を変更するだけではうまく機能しません。現場にうまく根付かせるには、設計・システム・教育それぞれの準備がそろっていることが前提になります。
全体設計とルール徹底はセットで必要
まずは、運用ルールを整理し直すことが大切です。
どの商品に対して先入れ先出しを徹底するのか、例外はあるのかを明文化し、全関係者に共有しましょう。中途半端な導入は、かえって混乱を招きます。
WMS(倉庫管理システム)との連携で実現性が高まる
次に、WMSとロケーション設計を組み合わせて、先入れが自然に先出しになる仕組みをつくる必要があります。
物流代行や3PLを活用している場合は、委託先との連携や設定のすり合わせが重要です。現場任せにしてしまうと、せっかくのルールが形骸化しかねません。
教育・マニュアル整備が成果を左右する
最後に、作業者教育とマニュアル整備も欠かせません。
WMSのピッキング指示があっても、それを「なぜ守るのか」を理解できていないと、現場では手間を省く動きになりがちです。意図が伝わっていれば、作業負荷が高いときでも、優先順位を理解して行動してもらえるようになります。
まとめ:先入れ先出しを“現場で機能させる”ために
「先入れ先出し」は在庫管理の基本原則ですが、実際の現場では単純なルールでは済みません。むしろ、仕組み設計・ルール運用・人の動きがかみ合ってはじめて成立するプロセスです。
特にEC物流においては、SKUが多く、波動(出荷量や業務量が時期やイベントによって大きく変動すること)が大きいため、仕組みがなければ先入れ先出しは形だけになりがちです。「分かってはいるものの徹底できない」という現場の声もよく耳にします。
だからこそ、自社の物流体制を見直すうえで、改めてこの基本ルールを「どう現場で機能させるか」を考えることが、在庫精度とサービス品質を両立させる第一歩になるはずです。
EC物流の支援に強いパートナーを選ぶなら「LogiPath(ロジパス)」

パスクリエでは、EC事業の規模や取り扱い商品に合わせて、最適な物流体制を構築するパートナーとしてお客様をサポートしています。
・「先入れ先出し」を徹底したいが、人員や時間のリソースが不足している
・物流業務に追われ、ECサイトの運営に集中できない
・物流コストを見直したい
こうしたお悩みには、自社倉庫を持たない「ノンアセット型」の物流代行サービス『LogiPath(ロジパス)』がサポートいたします。物流のプロが、貴社に代わって先入れ先出しを含むすべての物流業務を代行することで、業務効率化とコスト削減を実現します。まずはお気軽にお問い合わせください。
▼60サイズ580円で始められる、従量課金制のEC物流サービス「LogiPath」
https://pathcrie.co.jp/logipath/